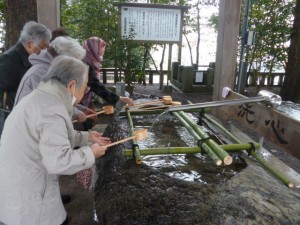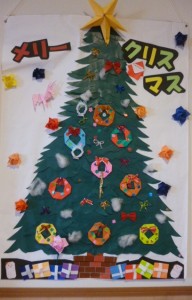ケアハウスキラッと白山の入居者様の一人が
2月4日がお誕生日だったとのこと…!!
お花を頂いたと職員までお話ししに来てくださいました☆
フリージアというお花がこの中にあり、
とてもいい香りだったとのこと(#^.^#)
フリージアという名前は、原産地の南アフリカで、
フリージアを発見した人が、親友の名前のフリーゼに献名して、
フリージアと名付けられたとのこと…!
なんだか素敵な名付けでほっこりしました(*^_^*)
キラッと白山の入居者様はお花が大好きな方が多いので
これからもこうしてお花の情報を共有していきたいなと思います♪
お誕生日おめでとうございます!
みなさん元気に過ごしていただけるよう職員一同
精一杯がんばっていきます!!















 珍しくこんなにも雪が積もりました\(◎o◎)/!
珍しくこんなにも雪が積もりました\(◎o◎)/!